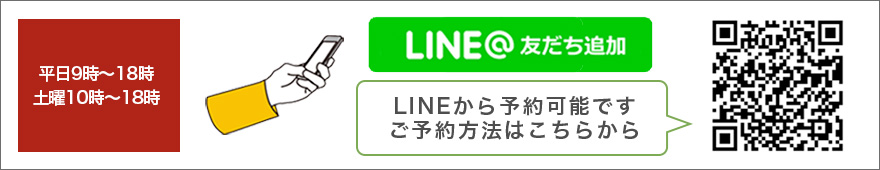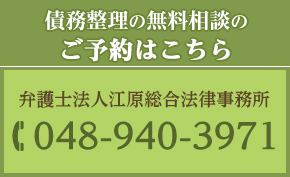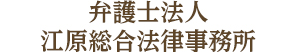家賃滞納で自己破産…住み続けられる?新たに借りられる?解決事例付きでわかりやすく解説
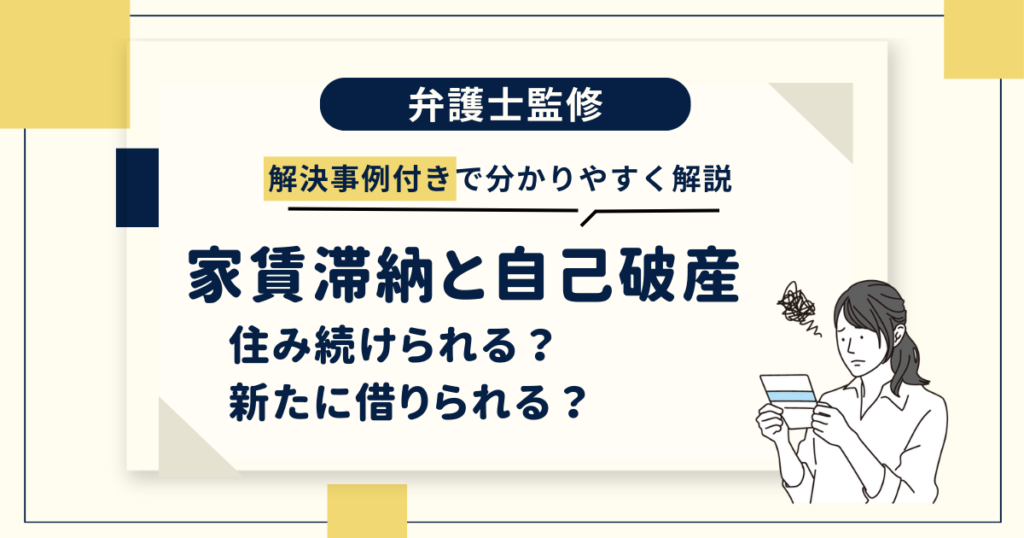
経済的な事情により、家賃を滞納してしまうケースは少なくありません。収入の減少や、病気など、さまざまな理由で家賃の支払いが困難になり、気づけば数か月分の滞納が発生してしまうこともあります。
家賃滞納が続くと、賃貸人や保証会社から督促を受け、最終的には賃貸借契約の解除、さらには強制退去を求められる可能性があります。滞納額が大きくなり、他の借金も溜まると「自己破産をした方がいいのでは?」と考える方もいるでしょう。
本記事では、家賃滞納と自己破産の関係をわかりやすく解説し、「自己破産で家賃は免除されるのか?」「今の家に住み続けられるのか?」「自己破産後に部屋を借りられるのか?」など、よくある疑問に弁護士がお答えします。さらに、自己破産以外の選択肢、実際の解決事例も紹介し、今後の判断に役立つ情報を網羅しました。
ひとりで悩まず、まずは正しい情報を知ることから始めましょう。
目次
1. はじめに|家賃滞納と自己破産の関係とは
家賃の支払いが難しくなると、「どうにかしなければ」「住む場所を失うかもしれない」「自己破産するしかないのか」と、不安や焦りを感じる方も多いのではないでしょうか。
本章では、家賃滞納が自己破産でどのように扱われるのか、また、自己破産によって住居にどのような影響があるのかを、全体像としてわかりやすく解説していきます。
(1) 滞納家賃も「借金」として扱われる
消費者金融からの借入れやクレジットカードの利用残高と同様に、家賃の滞納も「負債(借金)」として扱われます。
実際に、自己破産の申立てにおいては、滞納中の家賃も他の借金と同様に、「賃貸人(大家さん)」や「保証会社」を債権者として申告することになります。これにより、滞納家賃も破産手続の対象に含められます。
また、裁判所から免責が許可された場合は、支払義務が免除されます。
(2) 「住まい」は自己破産と切り離せない問題
家賃滞納と住居の問題は、自己破産における重要な検討事項のひとつです。
というのも、自己破産をすることで「現在の住まいに住み続けられるのか」「破産したのに新たに賃貸借契約を結べるのか」といった、生活の基盤となる住居について現実的な問題が生じるためです。
家賃の滞納状況や保証会社の有無、賃貸人(大家さん)との信頼関係等によって、その後の住環境に影響を与えることがあります。
2. 家賃滞納は自己破産で免責されるのか

「家賃の滞納分は、自己破産すればすべて帳消しになるの?」
これは多くの方が気になる疑問です。確かに自己破産手続(免責手続)は税金など一部の例外を除いて借金の支払義務が免除される手続ですが、滞納家賃がすべて免責されるとは限りません。ここでは、自己破産の前後で滞納家賃がどう扱われるのか、また保証人がいる場合はどうなるのかを、具体的に解説していきます。
(1) 自己破産前に滞納した場合は「免責の対象になる」
自己破産前、正確に言うと裁判所による「破産手続開始決定前」に発生した家賃滞納分は、原則として自己破産(免責)の対象となります(対象となるだけであり、必ず免責されるとは限りません)。
破産法では、破産手続開始決定前に発生した債務を「破産債権」として扱い、裁判所から別途免責許可の決定が出れば、これに対する支払義務は免除されるのが原則です。
未払家賃も他の借金と同様に支払義務が免除されます。
(2) 自己破産後に滞納した家賃は「免責されない」
自己破産後、正確に言うと裁判所による「破産手続開始決定後」に発生した家賃滞納分は、免責の対象になりません。
破産手続開始決定後に発生する負債(債務)は、破産手続の対象外となるからです。
たとえば、破産手続開始決定後に住んでいた賃貸住宅の家賃を滞納した場合、それは破産後の新たな債務として扱われ、大家さんや保証会社等から請求され続けることになります。たとえ免責の許可を得たとしても、免責の対象とはならないため、開始決定後に発生した家賃の支払義務は免除されません。
(3) 保証人がいる場合、免責の効果は保証人に及ばない
自己破産をしても、保証人の支払義務まで免除されるわけではありません。
保証人は、主たる債務者(賃借人・契約者本人)がその債務を履行できない(家賃の支払いができない)場合に、その者に代わって支払う法的義務を負っており、本人が支払えなくなった場合には、滞納した家賃について保証人に請求が及ぶことになります。
自己破産と免責手続の対象は、あくまで申立人本人の負債に限られます。免責許可決定が出ても、その効果は保証人には及ばず、保証人の法的義務は影響を受けないため、家賃の返済を求められます。
そのため、親戚や知人が保証人になっている場合、後でトラブルになることもありますので、保証人がついている場合は、事前に事情を説明しておくことをおすすめします。
3. 自己破産しても現在の家に住み続けられる?

「自己破産すると今のアパートから追い出されるのでは…」という不安を抱く方は多くいます。家賃の滞納があるかどうか、そして家主や管理会社等の対応によって結論は変わってきます。この章では、自己破産後に今の家に住み続けられるかどうかを、ケースごとにわかりやすく解説します。
(1) 家賃を滞納していない場合は住み続けられる可能性が高い
個人が居住目的で借りているアパートやマンションについては、破産手続開始決定後も賃料を支払い続けていれば、多くの場合、退去を求められる可能性は低いといえます。
賃貸借契約書には、「借主が破産した場合には契約を解除できる」といった特約が記載されていることもありますが、破産したという理由だけで契約を解除することは、実務ではあまり多くないといえます。
したがって、自己破産を理由にただちに退去を迫られることはあまりないと言えるでしょう。
(2) 家賃を滞納している場合は立ち退きになる可能性も
家賃の滞納がある場合には、「自己破産の有無にかかわらず」立ち退きを求められる可能性があります。
というのも、賃貸借契約において家賃の支払いは契約の根幹をなす借りている者の義務であり、その支払いを怠ることは債務不履行であり、契約解除の正当な理由となり得るためです。
一般的には、家賃の滞納が3ヶ月から6か月程度続いた場合、貸主に契約解除が認められ、最終的には、強制退去となるケースも少なくありません。
自己破産によって滞納分の支払義務が免除されたとしても、「居住を継続できるかどうか」は別の問題として判断されることに注意が必要です。
4. 自己破産後、新しく賃貸借契約を結べるか
自己破産をすると「新たに部屋を借りることはできないのでは?」と不安になるのは当然のことです。確かに信用情報に傷がつくことで審査に影響が出る可能性は考えられますが、だからといって全く部屋を借りられないわけではありません。
この章では、自己破産後に新しく賃貸契約を結ぶ際のポイントと注意点について詳しく解説します。
(1) 自己破産後も賃貸借契約は可能だが、審査は厳しくなる
自己破産後であっても、賃貸借契約を結ぶことは可能ですが、審査が厳しくなる傾向があります。
これは、自己破産をしたことで、信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されるため、保証会社の審査に通りにくくなるからです。
多くの賃貸物件では、入居の際に保証会社の審査が必要とされます。信用情報に事故情報がある場合、審査に通らず契約ができないケースもあるため、物件の選択肢が制限される可能性があります。
ただし、すべての保証会社が同じ審査基準を採用しているわけではありません。一社の審査に落ちたとしても、他の保証会社を利用すれば通過できる場合もあります。諦めずに選択肢を広げていくことが大切です。
(2) 保証会社を利用しない契約方法を検討するのも一案
保証会社を通さず、大家さんと直接契約する形で入居できる可能性もあります。
保証会社が使われない物件では、信用情報の審査が行われない場合があるからです。
地域密着型や比較的小規模な不動産会社や大家さん個人が管理する物件には、保証会社を利用せずに「連帯保証人のみ」で契約できるケースもあります。自己破産後でも、保証人の信用や本人の現在の収入状況が適切であれば、入居が可能となることもあります。
5. よくある質問:家賃滞納と自己破産に関する疑問を解消
自己破産と家賃滞納に関する情報は、専門的でわかりにくい点が多くあります。実際に相談を受ける中でも「住み続けられるのか?」「大家さんに伝えた方がいいのか?」といった具体的な疑問をいただきます。
この章では、そうした家賃滞納と借金に関するQ&Aをピックアップして、わかりやすくお答えします。
Q1. 家主には自己破産のことを伝えるべきですか?
家賃滞納がない場合は、必ずしも自己破産の事実を家主に伝える必要はありません。
自己破産は個人の借金を整理する手続であり、滞納がなければ契約関係に直接の影響はないからです。
家賃を滞りなく支払っていれば、破産したことだけを理由に契約を終了されることはほとんどないでしょう。
Q2. 家賃保証会社を利用している場合、自己破産の影響はありますか?
あります。滞納家賃を保証会社が立て替えて支払っている場合、その分は保証会社に対する債務(立替払いをしてくれた保証会社へ支払う義務)として、破産手続で処理されます。
滞納が長期にわたる場合には、契約解除や明渡し請求(いわゆる強制退去)を受けるリスクもあります。
Q3. 自己破産したことを不動産会社に知られますか?
基本的に、こちらから申告しない限り、不動産会社に知られることはあまりありません。自己破産をしたことを不動産会社に報告する義務も一般的にはありません。
ただし、新しく物件を借りる際に保証会社の審査がある場合は、信用情報を確認されるため、自己破産の履歴が審査に影響を与える可能性はあります。
Q4. 家賃滞納で訴訟を起こされていても自己破産できますか?
はい、明渡し訴訟中であっても自己破産の申立ては可能です。
ただし、裁判所の手続はそれぞれ別物のため、自己破産によって訴訟手続が自動的に止まるわけではありません。明渡し訴訟はそのまま進行することが多く、早急に引越し先を探すなどの対応が必要となる場合があります。
Q5. 家賃滞納後、保証人に対する請求はいつ頃きますか?
家賃の支払いが滞ると、借主が支払期日までに家賃を払わなかった時点で、保証人にも請求が届く可能性があります。
賃貸借契約における保証人は「連帯保証人」であることが多く、家賃の支払いがない場合、家主(貸主)は借主への催促を経ずに、いきなり連帯保証人に対して支払いを求めることができます。
たとえば、Aさんが2ヶ月家賃を滞納した場合、家主がAさんに請求するのと同時に、保証人に対しても直接請求の通知が届くことがあります。
6. 家賃滞納以外の借金問題:複合的な解決策
家賃の支払いが厳しくなると、「もう自己破産するしかない」と思い詰めてしまう方も多いでしょう。
しかし、自己破産以外にも検討できる法的手続や公的支援も存在します。この章では、自己破産に至る前に知っておきたい選択肢と、生活を支える制度について解説します。

(1) 自己破産以外の債務整理(任意整理・個人再生など)
自己破産以外にも、借金を整理できる手続があります。
債務整理には複数の種類があり、状況に応じて自己破産以外の方法も選択が可能です。
たとえば「任意整理」は、利息カットや返済期間の延長により毎月の負担を軽くできます。債務整理の対象を任意に選べるので、家賃以外の借金を任意整理するなど柔軟な選択が可能です。
また「個人再生」は借金を大幅に減額でき、自己破産に比べて生活への影響が少ない(例:資格制限がない)有効な手段といえます。
(2) 生活保護や支援制度の活用法
収入や資産が一定以下であれば、生活保護や各種支援制度を利用して生活の立て直しが図れます。
生活に困窮する状況では、国や自治体の制度を使って一時的に家賃や生活費の支援を受けることが可能です。
生活保護では、原則として住宅扶助(家賃相当額)も支給対象となります。家賃滞納による退去を防ぐためにも、早めの相談が肝心です。
(3) 弁護士に相談するメリット
借金や家賃滞納に悩んだときは、まず弁護士に相談することが、解決への近道となります。
なぜなら、状況に応じて最適な解決策を提案してもらえるからです。
弁護士は、自己破産をはじめとする債務整理手続はもちろん、家賃滞納に関する問題など、幅広い法律問題に対応できる専門家です。
不安な状況の中一人で抱え込まず、早い段階で第三者の視点を取り入れることが、問題解決に向けて非常に有効です。
7. 事例紹介|家賃滞納で訴訟に発展、転居後に自己破産して生活を再建
当事務所で実際にご依頼を受けた事例をご紹介します。
自己破産を選択することで、滞納家賃を含む借金の支払義務が免除されました。
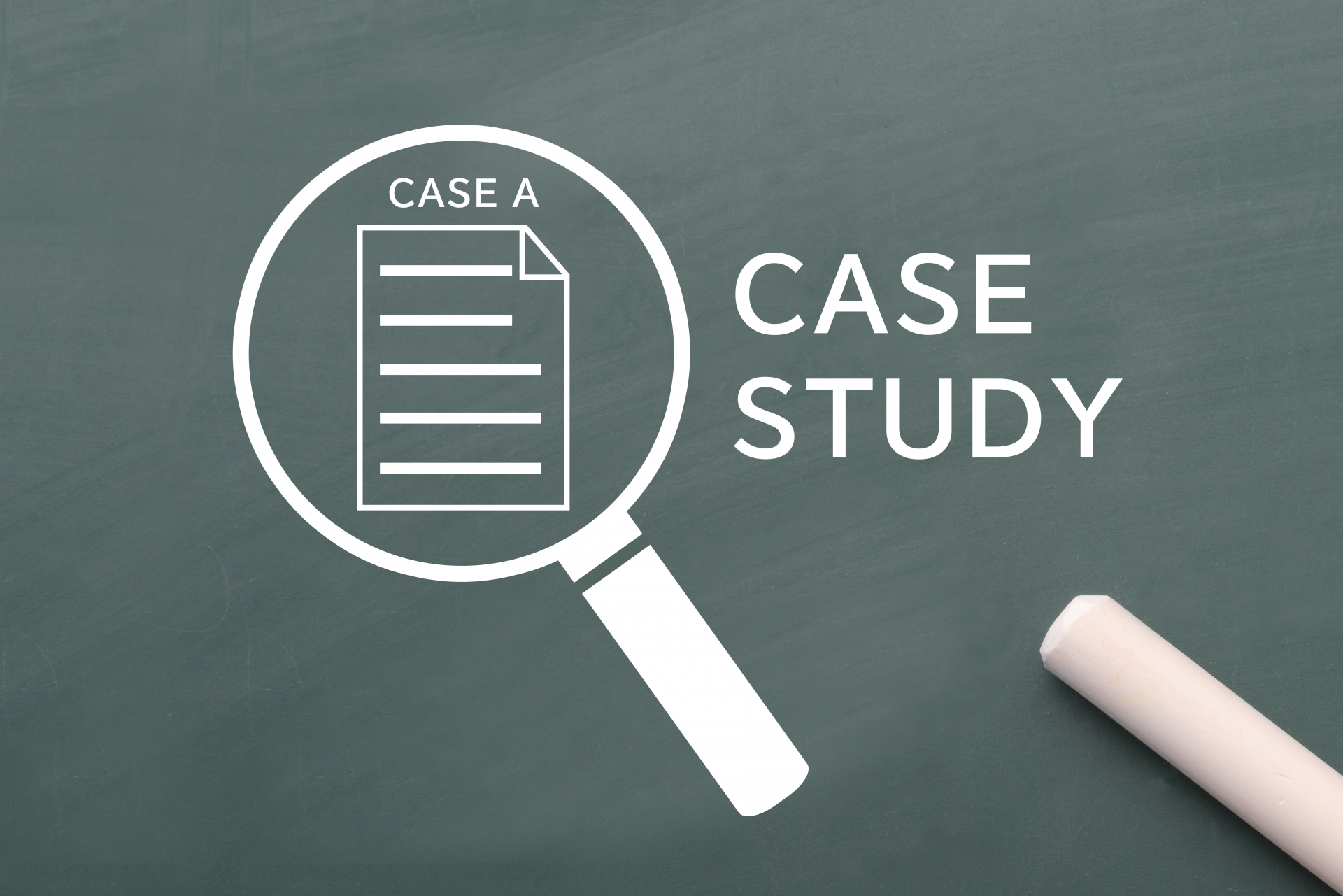
Aさんは会社員で安定した収入がありましたが、多額の借金を抱えており、家賃の滞納が続いたことから、大家さんから建物明渡し訴訟を提起され、当事務所にご相談に来られました。
免責不許可事由に該当する事情もなかったことから、弁護士は自己破産の申立てが適切であると判断しました。
ご依頼後、Aさんはまず引越し先の確保に取り組みました。すでに訴訟が進行しており、退去は避けられない状況だったためです。
Aさんは滞納していた物件の保証会社の担当者からのアドバイスもあり、その後、Aさんは無事に審査を通過し、新たに賃貸借契約を結ぶことができました。こうして、引越し先を確保することができました。
その後、自己破産手続は順調に進み、裁判所から免責が許可されました。依頼者は新たな住居で生活を立て直し、再出発へと踏み出すことができました。
8. まとめ
家賃の滞納が続くと、退去や借金の不安に押しつぶされそうになるかもしれません。ですが、自己破産をはじめとした法的な手続を活用することで、解決への道は開けます。自己破産によって滞納家賃の支払い義務が免除される場合もありますが、今の住まいに住み続けられるかどうかは、状況によって異なります。
大切なのは、一人で悩まず、今の自分に合った解決策を冷静に選ぶことです。早めに弁護士などの専門家に相談することで、生活再建への第一歩を踏み出すことができます。
投稿ナビゲーション
お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
24時間受付
LINEでのお問い合わせ
平日9:00-18:00 土曜10:00-17:00
この記事の監修者
弁護士 黒澤 洋介
注力分野:管財事件、個人破産、個人再生(個人再生委員含む)

茨城県出身。横浜国立大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。
コメント:
近年は、裁判所から選任される破産管財人としての職務も多く、多方面で経験を積んでいます。法人破産などの中・大規模案件は所内でチームを作り、複数名の体制で対応することも可能です。まずはご相談ください。