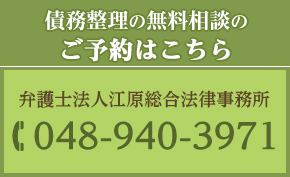マイホームを残したい方(住宅資金特別条項の活用)
個人再生事件の中で頻繁に用いられる「住宅資金特別条項」という言葉をご存知でしょうか。
本記事では、住宅資金特別条項について解説します。
個人再生手続は、法律の力を用いて借金を圧縮し、3年から5年の返済期間できまった金額を支払っていくのが基本となる手続です。
これとは別に、住宅ローンの支払いは継続し、住宅を確保できるという制度があります。
これを再生計画案に設ける必要があるのですが、住宅資金特別条項といわれます。
住宅ローンを組むと、融資を受けた金融機関やその保証会社などにより通常は自宅の土地建物に抵当権が設定されます。
この抵当権は、たとえ、個人再生手続が開始されたとしても、「別除権」として金融機関などの債権者が、原則自由に実行することができます。
つまり、滞納など諸条件が整えばいつでも抵当権を実行し売却を進めて貸付金の回収を図ることができるということです。
そして、再生手続が功を奏したとしても再生計画の効力は住宅ローン債権には及びません。
再生債務者は、住宅ローン以外の債権について再生計画に従い完済したとしても、住宅ローンにかかる抵当権を実行されてしまい住宅を手放さなければならないという過酷な状況に陥ります。
借金は整理できたが、住宅は残せなかったということになってしまいます。
そこで、そのような状態を回避するために法律で認められたのが、「住宅資金特別条項」という制度になります。
住宅資金特別条項には4つの種類が予定されています。
いずれも再生期間中に住宅ローンを支払続け、住宅を手放さなくて済むようにするための制度であることは共通していますが、予定されている場面によって、各類型の違いがでてきます。簡単にご説明します。
① 期限の利益回復型
② リスケジュール型
③ 元本猶予期間併用型
④ 同意型
① 期限の利益回復型
住宅資金特別条項の原則型です。
履行遅滞に陥っている部分と、そうでない部分を再生計画期間内に弁済することで再生手続開始前に発生した期限の利益の喪失の効果を消滅させるものです。
② リスケジュール型
利息や遅延損害金をすべて支払うことを前提とし、支払期限を最長10年間、再生債務者が70歳を超えない範囲内で延長して、その分、各回の支払金額を減額するというものです。
70歳を超えないというところがネックになり、実務上は、あまり利用されておりません。
③ 元本猶予期間併用型
②型の要件に加えて、定められた再生計画期間内は、債務の元本の一部猶予を可能とします。
他の一般再生債権の弁済との調和を図った計画を可能とするところに特色があります。
②型と同様、当初の約定返済の終期の時点で再生債務者が70歳を超えている場合には用いることができず、実務ではあまり用いられません。
④ 同意型
住宅資金貸付債権者の同意がある場合に認められる類型です。
基本的には、①型から③型とは異なる権利変更の内容とする条項を定めることができますので、比較的柔軟な型となります。
履行遅滞になっている事案では、実務上、この④型を選択することが多いといえます。
民事再生法の規定は、①型を原則としています。
①型では履行可能性が認められない場合にはじめて②型が利用できます。
以下同様に、②型で履行可能性が認められない場合に③型が利用できるという制度の仕組みになっています。
他方④型については、上記のようなルールはなく、住宅資金貸付債権者の同意があれば定めることができます。したがって、この場合、事案に応じた柔軟な対応も可能になるといえます。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を定めた場合、権利の変更によって期限の利益の回復及び弁済期間の延長は可能ですが、住宅ローンの元本弁済総額は変わらず、利息、遅延損害金も免除の対象にならないのが原則です。
例外的に上記④型の場合、債権者の同意がある場合はその限りではありません。
住宅資金特別条項が利用できる要件
住宅資金特別条項を利用するためには、一般に住宅ローン債務とよばれる債務(債権)が「住宅資金貸付債権」としての性質を備えていなければなりません。
住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金、又は住宅の改良に必要な資金の貸し付けに係る分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人の求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されているものをいいます(民事再生法196条3号)。
一般的にマイホームを購入する際に契約する住宅ローン債務(債権)は上記の「住宅資金貸付債権」に該当することがほとんどです。
ここでは、法的に問題となるケースをご紹介します。
Case1. 住宅ローンを組んでいるその建物が「住宅」といえるのか
例えば、個人事業で小売店を営んでいるなど自宅兼店舗として利用している建物がこの場合の「住宅」といえるのか、という問題があります。
住宅資金特別条項は、一定の条件のもと、再生債務者が生活の本拠である住宅を手放すことなく経済的再出発を図れるようにする点に主眼があるため、自宅とは名ばかりで、そのほとんどが店舗として利用されているケースにまで住宅資金特別条項を利用できるようにしなくてもよいとなってしまうからです。
「住宅」とは、以下の4つの要件を満たすことが必要となります。
① 個人である再生債務者が所有する建物であること
② 再生債務者が自己の居住の用に供する建物であること
③ 建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されること
④ ①~③を充たす建物が複数ある場合、再生債務者が主として居住の用に供する一つの建物であることの。
上記のケースは、要件③が問題となりえます。
自宅兼店舗として、建物の大部分(2分の1以上)を店舗利用している場合、「住宅」とはいえなくなり、住宅資金特別条項を利用することができなくなる可能性が高いといえます。
再生債務者自身が住宅ローンを組んで購入した家でも、再生債務者は一度も居住したことなく親族が居住している家は「住宅」といえるのか、といった問題もあります。
この場合は、要件②に関連し問題があり、再生債務者自身が一度も居住していないとなれば、「自己の」居住の用に供しているとは必ずしもいえないでしょうから、やはり「住宅」には該当せず、住宅資金特別条項は利用できない可能性が高いとなります。
Case2. 住宅に住宅ローンとは別に諸費用ローンの抵当権が設定されている場合、その諸費用ローンは「住宅資金貸付債権」といえるのか
前述のとおり、住宅資金特別条項を定めることができるのは、住宅資金貸付債権だけです。
住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金、又は住宅の改良に必要な資金の貸し付けに係る分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人の求償権を担保するために抵当権が住宅に設定されているものをいいます。
諸費用ローンとは、不動産仲介手数料、登記手続費用、各税金などをまとめてローンとすることがあり、名称としてもろもろの費用ということで「諸費用ローン」とされます。常に「諸費用ローン」という名称が使用されるとは限りません。
必ずしも住宅の建設または購入に必要な資金とはいえない諸費用ローンは「住宅資金貸付債権」への該当性を肯定することが難しいという判断になります。
もちろん上記は、あくまで一つのモデルケースをご紹介したもので、必ずしも画一的な判断がなされるというものではありません。
実際の運用や実務は、より複雑になっています。
個人再生事件のことでご質問、お困りのことがある場合は、ご遠慮なく当事務所にご相談ください。
お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
24時間受付
LINEでのお問い合わせ
平日9:00-18:00 土曜10:00-17:00
この記事の監修者
弁護士 石川 麗子
注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

千葉県出身。慶応義塾大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。
コメント:
弊所は地域に根付いた親しみやすい弁護士事務所です。私自身も気軽に相談できるような身近な存在でありたいと思っております。女性弁護士が2名在籍しており、同姓のお客様から相談を受けることも多いです。